
|
今回は唐の顔真卿の楷書、東方朔画賛を臨書します。 |

|
第1回 |

|
第2回 |
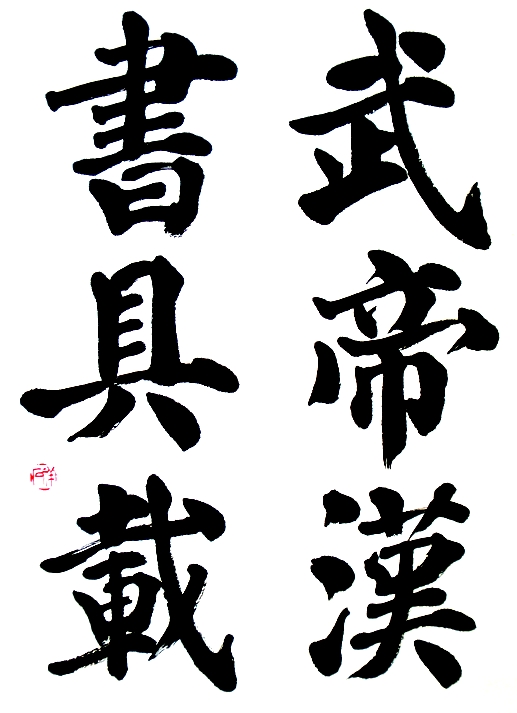
|
第3回 |

|
第4回 |
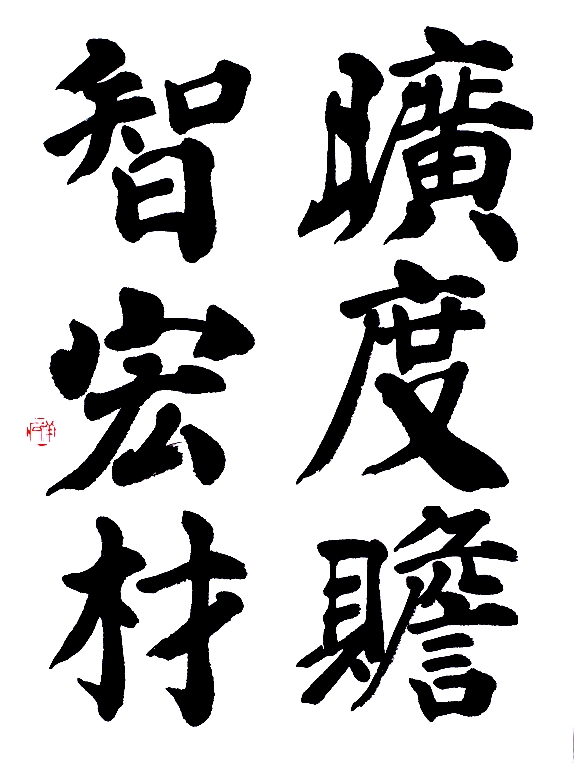
|
第5回 |

|
第6回 |
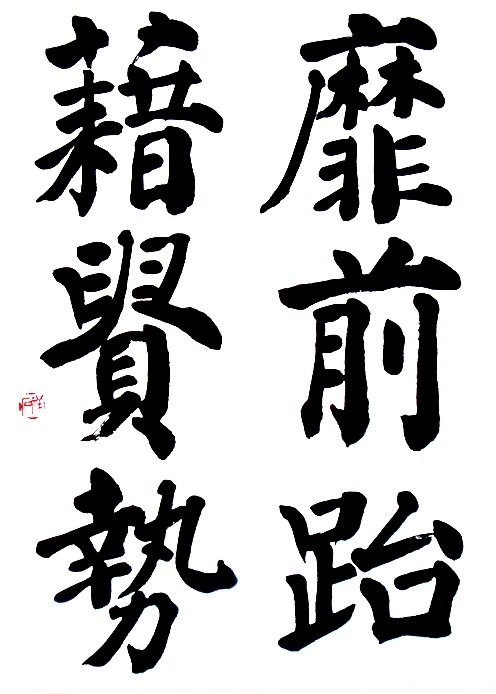
|
第7回 |

|
第8回 |
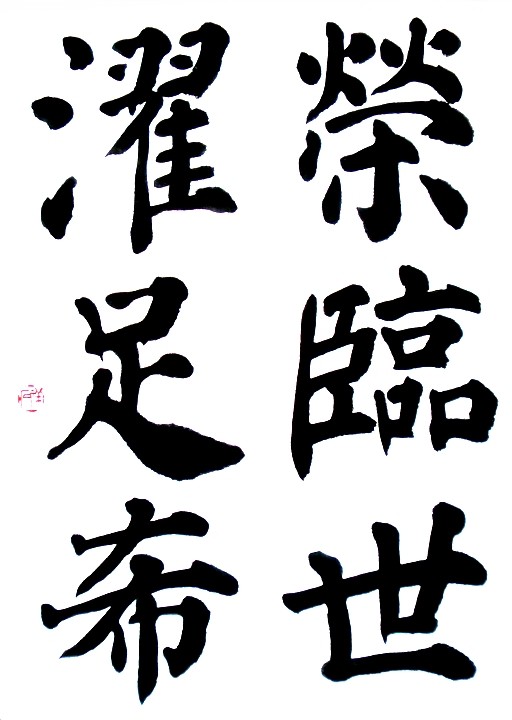
|
第9回 |

|
第10回 |
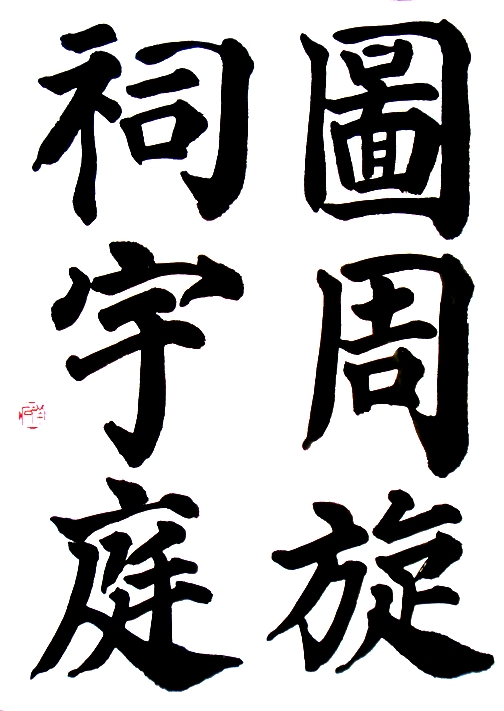
|
第11回 |
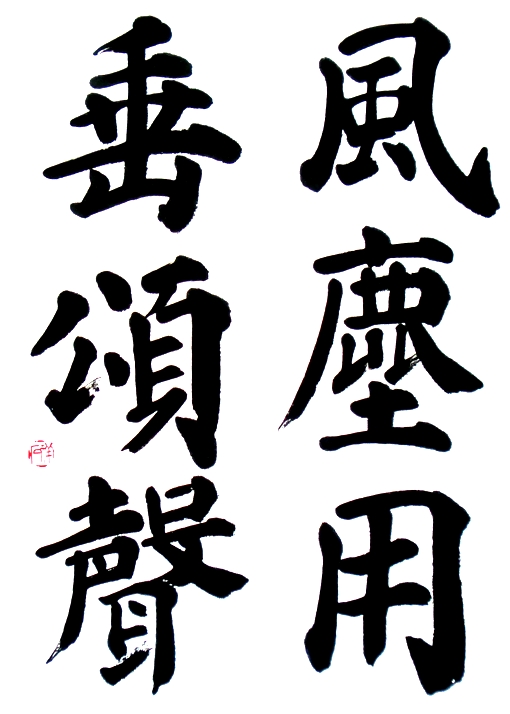
|
第12回 |